解雇規制改革だったか、解雇規制緩和だったかよく覚えていませんが小泉進次郎が語ったこのフレーズは実は意味不明な言葉です。
解雇に規制はありません。
規制を改革すると言う行為がどういうことなのか分かりません。
規制緩和は英語で言うとderegulationですが本来は規制撤廃と訳した方が適切です。
日本においては雇用契約は片務契約になっています。
解雇とは俗に言う会社が従業員の首を切ることです。
法律的に言えば会社側から雇用契約を解消することです。
日本では会社側から正当な理由が無く一方的に雇用契約を解消することは出来ません。
従業員からは理由無く契約解消出来ます。この点を持って片務契約とする所以です。
もちろん就業規則に違反(契約違反)すればそれを理由に契約を解除出来ます。
懲戒解雇が一番いい例です。
日本においてこのような考え方がベースにになって雇用が扱われているのは従業員(被雇用者)を保護するためです。
会社都合による一方的解雇(契約解消)をアメリカではlayoffと言います。
日本ではlayoffは出来ません。
然るべき理由(事業所の廃止とか事業の撤退など)があって会社都合で雇用契約を解消することを合理化と言います。
合理化は出来ますがアメリカのlayoffとは別物です。
従業員に然るべき理由(就業規則違反に該当しないが契約違反とみなせるレベルの)があって雇用契約を解消することを普通解雇と呼びます。
通常その時は一か月分の給与を支払うこととなります。退職金も払わないといけません。
解雇理由が正当かどうかは解雇された者が労働局に訴えて行政庁の判断を求めることが出来ます。
行政庁の判断は被雇用者保護の観点から従業員よりになります。
行政庁の判断に不服な時は裁判を起こし司法の判断を求めることとなります。
判決も従業員よりになります。
以上が日本の雇用環境における解雇の現状です。
小泉進次郎が如何にトンチンカンなことを言っているかお分かりのことと思います。
表現を誤魔化して本質を悟られないようにしていますが小泉進次郎が言っている(言わされている)ことは日本的雇用慣行をさらに破壊して日本の労働市場をさらに流動化し大資本に都合のいい環境を作り出したいと言うことです。
竹中平蔵らによって派遣業法が作られて帰属性の高かった日本の勤労者が流動化し労働者が増えることで労働市場が形成されました。
ちなみにそれまでは日本にはマルクスのいう労働者は割合としてそんなにいませんでした。
労働者では無くサラリーマンが大半を占めていました。
そういう人たちを日本では勤労者と呼んでいました。
日本の労働組合は企業内労働組合が殆どで欧米のような産業別組合は国労や全逓や自治労や全日海など特殊な世界に限られていました。
竹中平蔵らによって持ち込まれた派遣業法とその後の派遣社員という労働者の出現よって日本は独特な日本的雇用慣行を破壊されました。
話が長くなるのでここで終わりにします。
最後に雇用契約は基本民民の契約です。最近日本は民民の契約に国家権力が介入し過ぎです。
新自由主義者やグローバリストの操り人形を総理大臣にしたら日本はさらに破壊されていきます。
小泉進次郎を担ぐ不届な自民党の国会議員は自民党から出ていけ。
解雇規制改革だったか、解雇規制緩和だったかよく覚えていませんが小泉進次郎が語ったこのフレーズは実は意味不明な言葉です。
 アンチグローバリズム
アンチグローバリズム
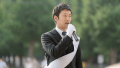

コメント